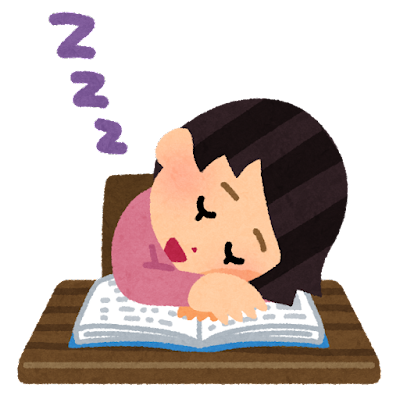ブログ
2019年 9月 5日 好奇心って大事。~横山先生~
こんにちは!
大学の成績発表があり、ほっと一息ついている横山です。
高校のテストと違い、全部論述であったりレポートで評価が決まったりと成績の予想がつかない授業が多く、毎度毎度ドキドキしています。
中には、教職に関する授業で「インターネットやタブレットを利用した教材と学習指導案を作りなさい」なんていう課題もあり、先生によって全然評価方法が違うんだなぁと感じています。
さて、今回のブログでは私が東進に通っていた時に好きだった講座について話したいと思います。
9月は学校が始まり疲れが出てきたりと、なかなか受講に集中できないときってありますよね。
眠くなってしまったり、なんだか集中出来なかったり・・・。
私はそんな時、とりあえず自分の好きな講座を受講していました。
私が一番好きだった講座は、林先生のハイレベル私大現代文トレーニングです!
何度かブログに書いているように、私は国語が一番好きだったのでその影響も強いと思います。
しかし、楽しかったことだけが理由ではありません!
この講座は毎回、私大で実際に出題された問題を解いていくのですが、これがなかなか難しい・・・。まだ私大対策に入っていないくらいから受講し始めたので、得意だと思っていた現代文が全然解けずに悔しい思いを感じつつ受講していくことに。
問題を解いて、間違えて、へぇ~と思いながら解説を聞いて、復習して・・・。
なんとなくこれを繰り返していたのですが、受講が終わるころには以前より格段に現代文の解き方が論理的になっていました。あら不思議。
自分で特にこれを意識した!というポイントは正直なところ薄いのですが、林先生の解法とその解説のセンスなのかなぁと思います。
受講中もキレッキレのツッコミを挟みながらの面白い解説がわかりやすく、90分全く飽きることなく集中できます。
それに加えてほんっとうに分かりやすい!
自分が受験を終えてみて、現代文が伸びた要因を考えた時に「絶対林先生の授業だよな~」と思ったほどです。
今回は現代文に特化した話になってしまいましたが、科目に関わらず自分が「面白い」と感じたものは吸収が早いですし、集中して勉強できます。東進で開催しているイベントや大学の説明会など、自分が興味を持てることをぜひたくさん見つけてみてください!
早稲田大学教育学部 2年 横山千咲
★明日の開閉館時間★
13:00~21:45
2019年 8月 30日 模試と過去問の共通点~田邊先生~
こんにちは!!田邊です!!
最近やっと暑さがぬけてきましたね、、
私は秋が一番好きなので早く秋になって欲しいです。
8月模試が終わって4日が経過しました。
復習は終わりましたか?
何度も口を酸っぱくして言うようですが、模試は復習が何よりも一番大事です。
本番のセンター試験で同じ問題が出たけど解けなかった、、なんてことがあったら後悔の塊です。
復習はすぐに終わらせましょう!!
さて、みなさん、二次私大の過去問は解き始めましたか?
「それはもちろん解きました~」
って声が聞こえてきます。
じゃあ復習も全部終わりましたか!?!?
「あ、いや、それはまだ採点も返ってきてないし、、終わってない、、」
なんて人!!!!
模試と同様、過去問で重要なのは復習です!!!!
東進の過去問講座には映像の解説授業がついてます。
自分のやり方で理解するだけではなくて先生から解法を教えてもらうこともとても重要です。
コンテンツを存分に利用して復習を念入りに行いましょう!
横浜国立大学経済学部経済学科1年
田邊優菜
★明日の開閉館時間★
8:00~20:30
2019年 8月 29日 朝起きて!!~不破先生~
こんにちは、不破です!
今回は朝早く起きて勉強することの大切さについて書こうと思います。
まず、9月1日から東進は通常開館に戻ってしまいます。
皆さん、この夏休み期間朝登校はできたでしょうか!部活や学校等でできなかった生徒もいるかもしれませんが、朝早く起きて勉強することは重要なのです!
本番の試験は朝から始まることが多いですよね。そのため、朝から集中して問題を解けるようになることが必要になってきます。それができるようになるために「普段から朝早く起きて勉強をすること」があるのです。
日頃から朝に勉強していなくても本番は取れると思っている子もいるかもしれません。ですが、そんな子ももしかしたら朝からの勉強習慣をつけていれば本当はもっと集中して解けるかもしれません!!
朝起きて約2時間程経たなければ脳があまり働かないと言われています。今のうちから朝早く起きて勉強する習慣をつけましょう!
慶應義塾大学看護医療学部1年 不破菜津子
★明日の開閉館時間★
8:00~20:30
2019年 8月 28日 入試問題って難しいよね。~鷲尾先生~
皆さんこんにちは、鷲尾です!
8月模試が終わり、夏休みが終わり、また学校が始まりますね。学校にはちゃんと行きましょう。
ところで、夏は満足のいくまで勉強できましたか?
模試がうまくいかなかった、夏休みあまり勉強できなかったと後悔することもいろいろあるかもしれません。
しかし終わったことはどうすることもできないですし、自分で振り返りをしたらあとはこれからのことを考えるようにしましょう。
夏の勉強がうまくいったならそれは素晴らしいことですし、そうでなくてもできなかったことを改善して9月以降の勉強に役立ててほしいです。
受験生が9月以降の勉強で必ずやることになるのが第一志望校の過去問です。
そこで今回は、過去問の使い方について少し話したいと思います。
過去問は難しいですし、合格平均点をとるのは大変です。なので初めて解いてみたら10%くらいしか点が取れなかったなんてこともあると思います。
でも、点数を気にする必要はないと思います。
今解けなかったとしても、受験当日までに解けるようになっていればそれでいいと思いませんか?
だから過去問を解くにあたって大切なのは解いたあと何をするかなのです。
じゃあなにするのか?
まずは当たり前ですが時間を図って過去問を解き、提出します。(理系の人は計算用紙を手元に残しておくようにしましょう。)
提出したら、分からなかった問題や時間が足りなくて解けなかった問題を解きなおします。わからないときは教科書や参考書を読み返したり問題集から類題を探すなどしてみるといいと思います。
次に解説授業を見て理解したら、過去問の解きなおしをしたり、また類題を探して解いてみるといいと思います。
ただ、その場で解きなおすと答えを覚えていて意味がないと考える人もいるので、そう思う人はいつ解きなおしをするか決めておくといいと思います。
これはあくまで個人の意見なので、自分でしっくりくるやり方を見つけて過去問をうまく使ってください。そうすれば志望校合格も見えてくると思います。
頑張ってください。
横浜国立大学 理工学部 情報工学EP 1年 鷲尾卓
★明日の開閉館時間★
8:00~20:30
2019年 8月 27日 過去問の進め方 ~小川先生~
こんにちは、小川です。
8月模試を受けた人、お疲れ様でした!よく復習して同じ間違いをくりかえさないようにしましょう。
後日受験の人は頑張ってください!
そろそろ秋になるということで、今回は私の二次私大の過去問の進め方について書こうとおもいます!
私は以下の3つのことを意識していました。
①一週間に一年分をめやすに進める。
②解いた次の日に解説授業で復習する。
③一回目はちゃんと制限時間どおりやる。
過去問の進め方は人それぞれだとおもいますが、復習だけはぜったいにちゃんとやりましょう!!
自分に一番あった方法を見つけて、がんばっていきましょう!
★明日の開閉館時間★
8:00~20:30